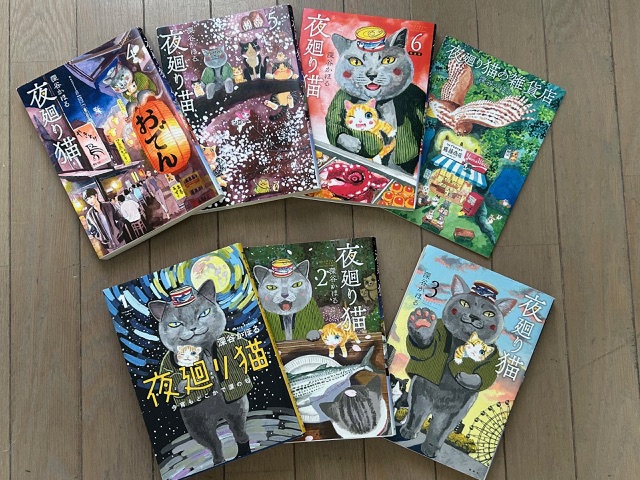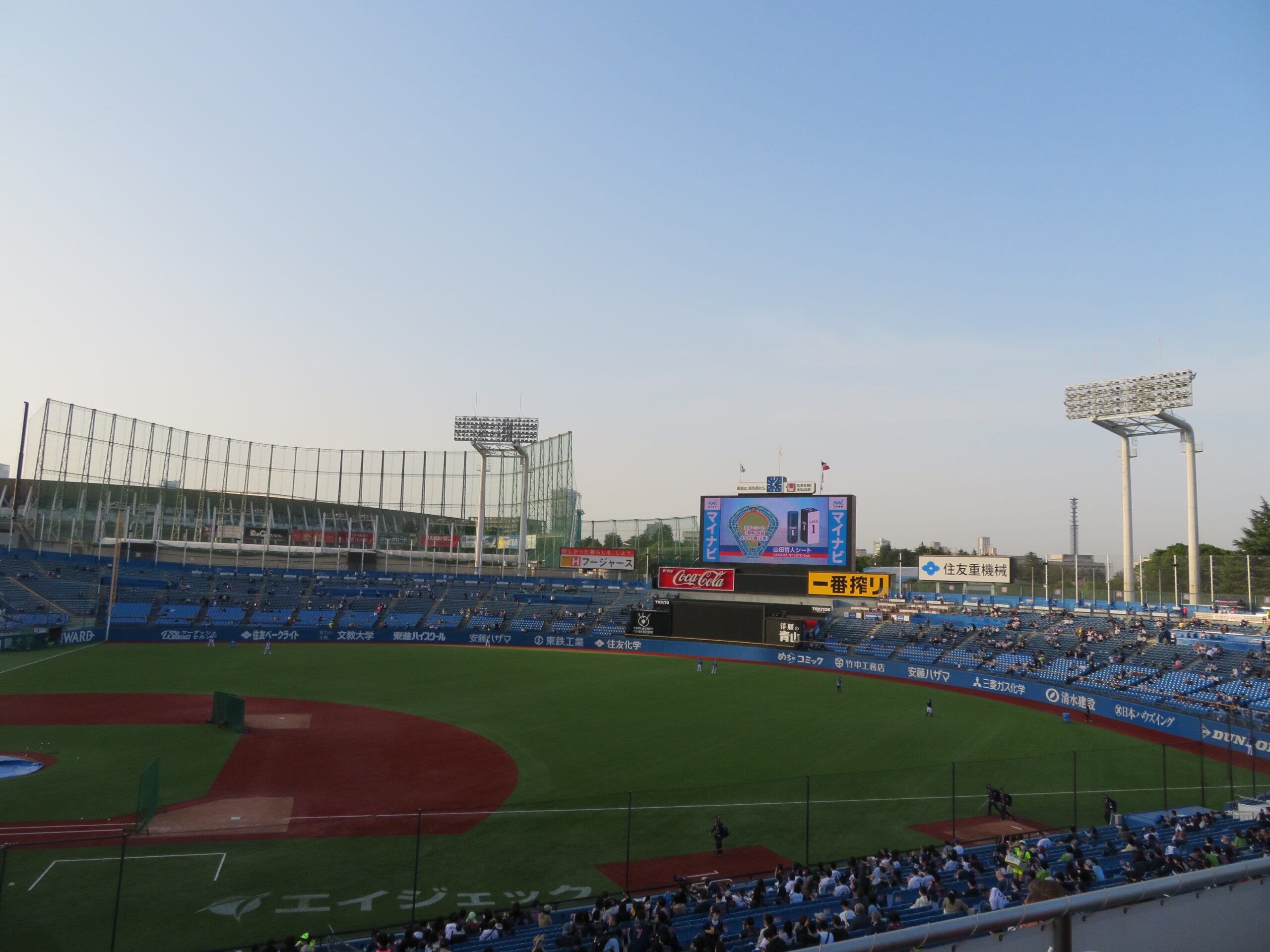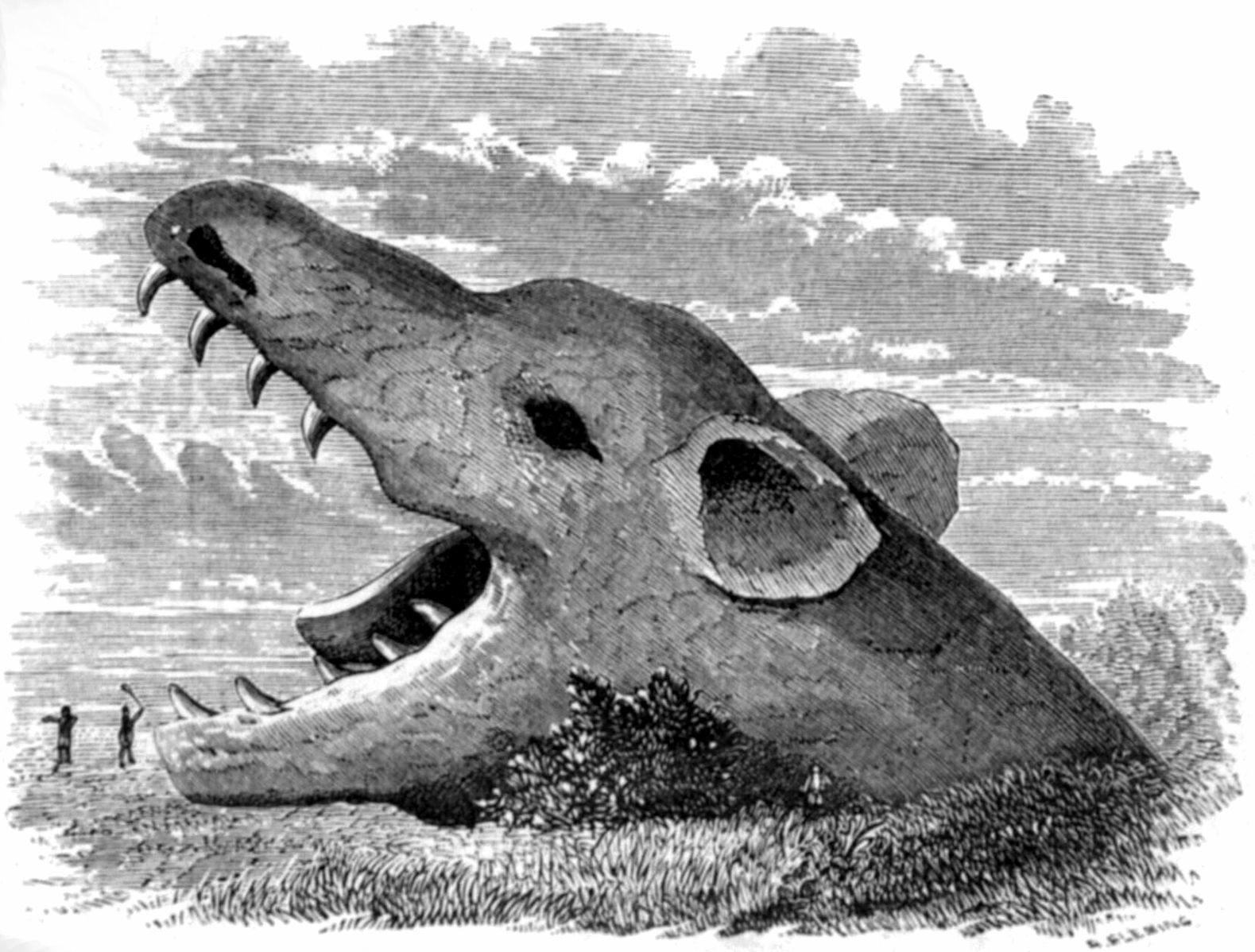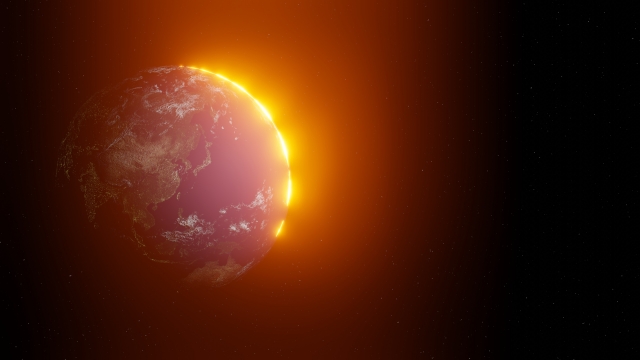カメラの周辺機器ヲタクがおすすめする手軽に買える便利機器7選
偏愛・脳汁を語るサイト「ヲトナ基地」では、多数の「愛しすぎておかしくなるほどの記事」をご紹介してまいります。 ヲトナ基地で今回紹介する記事は「カメラの周辺機器ヲタクがおすすめする手軽に買える便利機器7選」。地主恵亮さんが書かれたこの記事では、「カメラの周辺機器」への偏愛を語っていただきました!
写真や動画の撮影というものがある。今ではスマホで簡単に撮ることができるし、そのクオリティも高い。以前はコンデジをいろいろな企業が出していたけれど、スマホに取って代わられてしまった。
どうもこの記事を書いている地主です!
私は企画を考えたり、文章を書いたり、デザインをしたりする仕事をしているが、写真や動画も生業にしている。その時に使うのはミラーレス一眼というものだ。レンズを変えることができて、スマホより設定をいじれるので、私にとっては便利なアイテムである。
私が使っているのはソニーとパナソニックのミラーレス一眼(以下、カメラ)だ。ソニーとパナソニックは撮影するものによって使い分けているけれど、その時々の気分で決めたりするので、厳密な使い分けは特にない。今日は和食より中華の気分だな、みたいな使い分けだ。
パナソニックとソニーのカメラを使っています!
この記事ではカメラについてはあまり書かない。カメラも愛しているのだけれど、日々新製品のニュースを追いかけているものの、カメラは高いのだ。上記のソニーのカメラは安い方ではあるのだが、レンズとボディで70万円くらいしたと思う。だから、気軽に買うことは私のレベルでは難しい。
その結果、私はカメラの周辺機器を深く愛するに至った。撮影をより快適にしてくれるし、カメラと比べると安いのだ。便利そう! と思えば、お財布とあまり相談することなく買うことができる。今回はその中で便利だったものを紹介したい。
紹介するぜ!
1.三脚周辺(F38クイックリリース)
撮影で三脚を使う時がある。三脚とはカメラを任意の高さや角度で固定できるものだ。多くの三脚はプレートをカメラにつけて、三脚の雲台と呼ばれる部分に取り付ける。そのプレートはネジ式で、雲台側もネジ的なものをいじる必要があり、取り付けには時間がかかる。数回程度なら別にいいのだけれど、一度の撮影で何度も取り外しをやっていると面倒になってしまう。
そこで「Ulanzi FALCAM F38クイックリリース」
こうなります!
そこで私がいま全ての三脚につけているのが、「Ulanzi FALCAM F38クイックリリース」。プレートとベースがあり、プレートはカメラにつけて、ベースは三脚につける。これが本当に便利。プレートを複数購入して、それぞれのカメラにつけておけば、カメラを変えるごとに起きるプレートの交換が必要なくなる。
同じようにベースを複数の三脚につけておけば、どの三脚を使っても、カメラをワンタッチで固定することができる。
こうしておけば、(左カメラ、右三脚)
ワンタッチで、
三脚に固定できる!
こんなに素晴らしいものが世の中にあったのか、と驚いた。三脚は時と場合により違うものを使うことがあるのだ。その度にカメラ側にプレートをつけて、というのが煩わしくて仕方がなかった。それがこのFALCAM F38クイックリリースではないのだ。革命的に楽だ。
さらに「Ulanzi F38回転ズレ防止プレート」
ただ通常のF38のプレートは、緩みやすいという問題がある。そこで私は「Ulanzi F38回転ズレ防止プレート」を使っている。通常のものと違い、一面にだけ突起がついている。これが優秀でカメラに引っかかり緩むことがない。私は全てのカメラでこちらのタイプのプレートを使っている。
突起が引っかかり緩まない!
撮影中によくあるのだ。三脚を使っていなかったけれど、急に三脚で固定して撮らないといけない場面が。その時にこのシステムは本当に素早くできるので便利で、今やないことが考えられない。ありがとう、とこのメーカーに言いたい。
全ての三脚にベースをつけています!
2.三脚周辺(BENRO 3ウェイ雲台)
三脚は足と雲台に分かれている。雲台にはいくつかの種類がある。3ウェイ雲台や自由雲台、ギア雲台などだ。それぞれに良い面と悪い面があるのだけれど、私は「ギア雲台」を好んで使っている。
BENRO 3ウェイ雲台
ギア雲台は上を見るとキリがないほどの値段になるのだけれど、「BENRO 3ウェイ雲台」は実売だと2万円弱と安い。ガタつくこともなくて値段以上の満足感があった。ちなみに三脚には規格があるので、私はManfrottoを足で使っているけれど、別のメーカーであるこの雲台を取り付けることができる。
ギア雲台はダイアル的なものを回せば、ミリ単位で位置を調整できる。ほんの少しを調整するのに向いているのだ。なかなかに便利だ。
ダイアルでわずかな調整も可能!
3.三脚周辺(Ulanzi ビデオ雲台 F38クイックシュー付き)
私は写真だけではなく動画の撮影も行う。現場では写真がメインだけれど、急に動画を撮る場面も出てくる。写真と動画では三脚が異なるのだけれど、両方の三脚を持って行くのは面倒、というか重い。車では行けないようなところで撮影することもあるからね。
そこで「Ulanzi ビデオ雲台 F38クイックシュー付き」
そんな時は「Ulanzi ビデオ雲台 F38クイックシュー付き」の出番。通常の写真用の雲台の上にこれを設置すれば動画用の雲台に変わる。カメラを被写体に合わせて滑らかに動かすことができるのだ。これは買った時からF38のベースがついているので、カメラにF38のプレートをつけておけば、すぐにカメラを固定することができる。
F38のベースがあるので、
プレートをカメラにつけておけば簡単に取り外しができる!
さらに私は「Ulanzi ビデオ雲台 F38クイックシュー付き」の下部にもF38のベースを付けている。そのため土台となる写真用の雲台(こちらにももちろんF38のプレートを常につけている)に簡単に固定できる。マジで便利。大体において撮影はおしていることが多いので、少しでも早く準備がしたいのだ。
下部にF38のプレートをつけているので、
土台となる雲台に簡単に取り付けられる!
ただ動画用の雲台としては簡易なものであり、本来の動画用の雲台に比べれば、滑らかさに劣るし、バランスも悪い。ただ使えないかと言えばそんなことはなくて、割とよく使っている。むしろ小さくて持ち運びが便利で助かっている。
ちょっと不安定な感じはあるけど大丈夫!
4.ネジ周辺(SmallRig 折りたたみドライバー)
カメラに周辺機器を取り付ける時はネジが使われることが多い。先に紹介したF38もそうだ。F38の場合は10円玉とかでもネジを回せるのだけれど、より強固にネジを止めようと思うとドライバー的なものが必要だ。もちろん10円玉で回せないネジの時も多い。
そこで「SmallRig 折りたたみドライバー」
カメラ系で使いそうなドライバーが一つにまとまっているのが「SmallRig 折りたたみドライバー」。これひとつあれば、ドライバーを複数持ち歩く必要がないので便利。これを買ってから困ったことがない。ここにあるだけで大体足りるのだ。しかも、小さい。SmallRigにありがとう、と言いたい。カメラのケージもSmallRig一択で使っている。
これだけあるんだぜ!
5.カメラ周辺(Ulanzi カメラ用冷却ファン)
写真撮影では私は体験したことがないのだけれど、動画撮影では熱暴走ということが起きる。私が使っているパナソニックのGH6はカメラにファンがついているので、熱暴走は起きないのだけれど、ソニーのカメラではたまに起きる。起きてデータが全て消えたこともある。
そこで「Ulanzi カメラ用冷却ファン」
そこで「Ulanzi カメラ用冷却ファン」だ。カメラに後付けできるファンで、取り外しも楽。動画撮影なのでファンの音がうるさいと、マイクが音を拾ってしまい困るのだけれど、この商品は静かなので大変重宝している。
バネ式で、
このように取り付けます!
こんな小さいファンで変わるの? と思うかもしれないけれど、変わります。めちゃくちゃ変わります。同じ環境で熱暴走したカメラが、これをつけると熱暴走しなかった経験があります。なのでめちゃくちゃ感謝しております。
基本的にはいろいろなカメラにつけることができます!
6.バッグ(HAKUBA 防水インナーバッグ ドライ クッションポーチ)
カメラは基本的には水に弱い。防塵防滴だとしても濡れない方がいいと思っている。ただ雨は降ります。急に降ります。降らないで、と願うのに降ります。リュックサックなどに入れていても、リュックが濡れて中まで濡れることもあります。
そこで「HAKUBA 防水インナーバッグ ドライ クッションポーチ」
そこで私が愛用しているのが「HAKUBA 防水インナーバッグ ドライ クッションポーチ」。防水のカメラポーチなのだ。カメラ用ではない防水バッグもあるけれど、こちらは完全防水生地だけではなく、衝撃を吸収するクッション素材も使われている。つまり水からも衝撃からも守ってくれるのだ。
裏はこんな感じ! クッション素材!
乾燥剤を一緒に入れておけば、より安心という感じで、私はカメラをサブを含めると4台ほど使っているのだけれど、全てにこのポーチを使っている。取り出すのもそこまで手間ではないし、濡れないという安心は何事にも変え難い。このポーチ以外、今では考えられない。耐久性もいい気がする。
閉めるとこういう感じです!
7.ストラップ(PeakDesignアンカーリンクス)
カメラには首にかけることができるストラップをつけている。ただ三脚に設置する時はこのストラップが邪魔になってくる。ただストラップの取り外しは面倒だ。ここに通して、ここで固定してとかしないといけないから。
そこで「PeakDesignアンカーリンクス」
そんな問題が「PeakDesignアンカーリンクス」で解決する。カメラを使っている人には定番のアイテムだ。アンカーをカメラ側に取り付け、アンカーハウジングをストラップにつける。すると簡単にストラップとカメラを分離することができる。
簡単に取り外しできる!
「あると便利」から、ないと無理になる
以上が最近よく使っているカメラの周辺機器だ。アイデア商品のようなもので、いろいろなメーカーから、いろいろな商品が頻繁に登場している。最初は嘘でしょ、と思うのだけれど、使うと痒いところに手が届くという感じで、最終的にはもはやないと撮影できないになるから驚く。なかった頃には戻れないのだ。あと、カメラと比べれば安いからダメ元で買ってみるか、もできる。
みんなカメラの周辺機器買おうぜ!