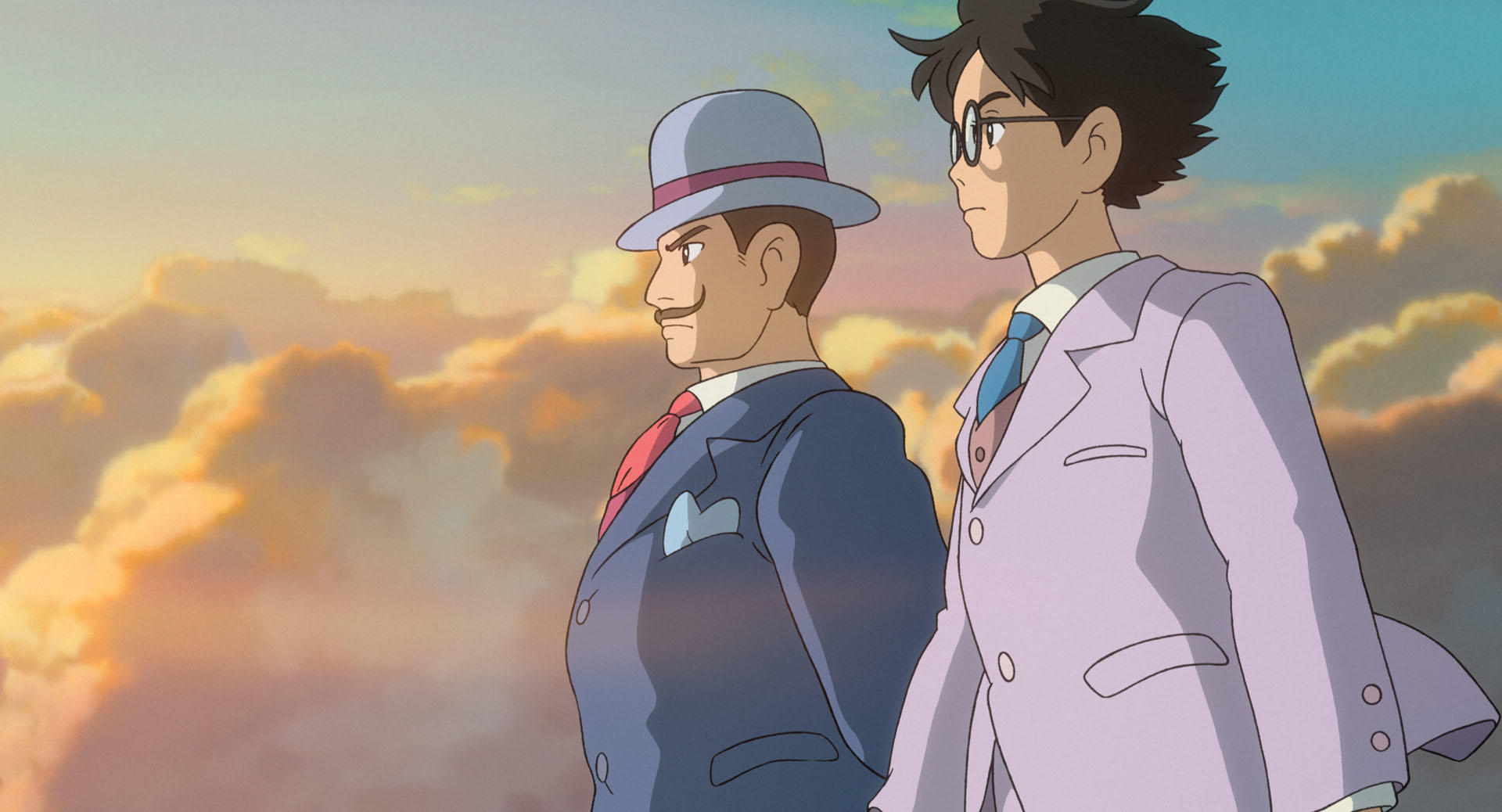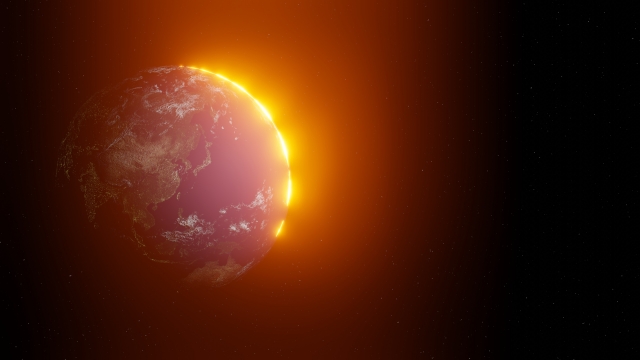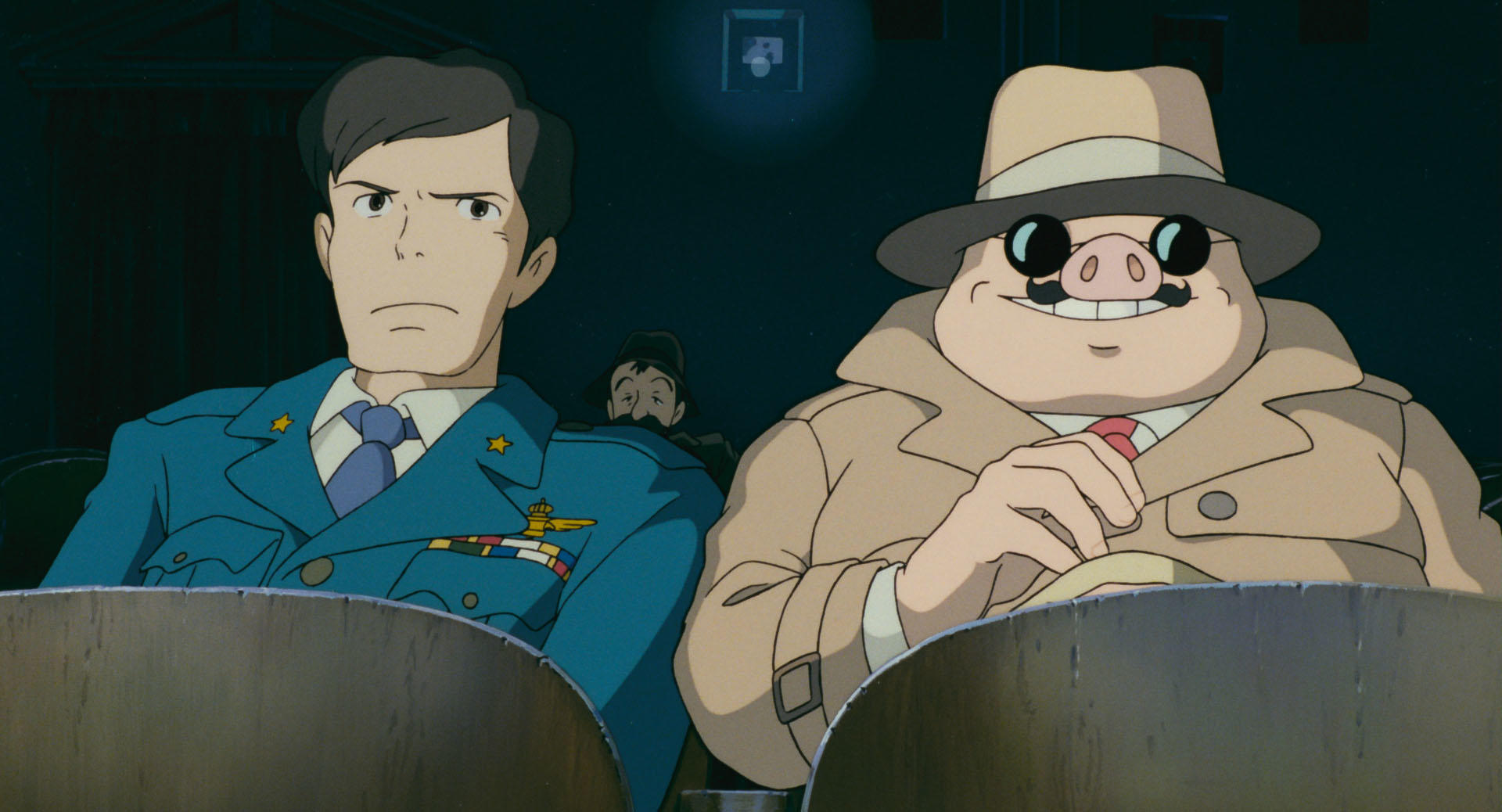全マンガ読み必読の「埋もれた」超傑作『ヴァンパイア十字界』をネタバレ抜きで紹介する。

「大事なものを失ったのがどうした 這い回ったのがどうした 復讐を否定されたのがどうした それくらい私だって見たぞ ――いや それ以上のものさえ私は見ている お前はまだずっとましだ そんなもので支えられた剣を私に誇るな 私を殺したければ 私以上の地獄を見つけるがいい」
引用:城平京&木村有香『ヴァンパイア十字界』
埋もれた傑作などめったにないはずだが――あった。
それは、物語を愛する人々の心に宿るひとつの甘い幻想である。
どこかに、その破格の内容にもかかわらず、あまり知られていない、あるいは不当に評価されている「埋もれた大傑作」があるのではないか。その作品は、真にその作品を愛でるべき読者の手がとどかないまま、いまも膨大な出版物の山のなかに静かに眠っているのではないか。そういう、いかにも甘すぎるファンタジー。
現実には、とくにこのインターネット時代においては、そのような作品が存在する可能性は限りなく低い。
いまでは、どれほどマイナーな場所で発表された作品であろうと、だれかが見出し、正当に評価し、光をあてて情報を広めるものであり、埋もれた傑作がいつまでも埋もれている可能性はほとんどないのだ。
そう、ずっと埋もれたままの傑作など、まず、ない。そう断言してもかまわないように思われる。じっさい、わたしもまったく思いつかない――たったひとつの「例外」を除いては。
その唯一無二の「例外現象」こそがこの『ヴァンパイア十字界』なのだ。
緻密に練られた構成、幾たびとなくくり返す逆転、ドラマティックかつ悲劇的な物語、長く印象に残るキャラクター。いずれも、いままで読んできた物語のなかで最高水準であり、読後には唖然として言葉が出ないレベルの傑作というしかない。
原作の城平京が手がけたマンガ作品には素晴らしいものが多いが、そのなかでも圧巻の最高傑作というべきであろう。
あるいは、2000年代に発表されたすべてのマンガのなかでも、たとえば『進撃の巨人』などと並び最高峰を争う名作であることに、わたしはまったく疑いを抱かない。
だが、それにもかかわらずこの至上の作品は十分に読まれ、評価されているとはいいがたい。
もちろん、一定の層には読まれているし、最後まで読み終えた人の評価は総じて高いのだが、それでも、その内容の充実さを考えると、やはり「埋もれてしまった」作品と見ることが正しそうだ。
城平京の他の作品には『スパイラル ~推理の絆~』『絶園のテンペスト』『虚構推理』などアニメ化され、好評を博した有名作品が多々あるだけに、かれが手がけたマンガのなかでも白眉ともいうべきこの『ヴァンパイア十字界』が広く知られていないことはあまりにも惜しく感じられる。
これこそまさに「もっと評価されるべき」真のマスターピースだ。
あなたがもし、まだこの魂の物語を読んでいないのだとすれば、どうかわたしの言葉を信じていますぐ読んでみてほしい。
全九巻とコンパクトにまとまっており、一気に読み上げてしまうこともできると思う。読後には最高の満足感が待ち受けていることを保証する。
ほんとうにほんとうに素晴らしい物語だけが持つ、ため息すら出ないような感動。この作品はそういった格別の読後感をあたえてくれる、数少ない本物の名作のなかの一つなのである。
なぜ、この名作は埋もれたのか。
ただ、正直にいえば、それでもなお、十分に高く広く正しく評価されることなく「埋もれた傑作」になってしまった理由もわからないではないのだ。
一つには、作品のリアリティラインの問題がある。物語は「国を失ったヴァンパイアの王」ローズレッド・ストラウスの一千年の時をかけた長い旅から始まり、その後、じつに意外な方向へ二転三転していくことになるのだが、その構想の雄大さは最初の時点ではまったく見えないといって良い。
初めのあたりはごく凡庸な「中二病」のファンタジーと見える、いや、そうとしか見えないのである。
かつて、マンガ批評家の伊藤剛は名著『テヅカ・イズ・デッド』の冒頭において、「ガンガン系」のマンガが偏見の目にさらされ不当に低い評価を受けている事実を指摘し、そのような見方を批判したが、そうはいっても「ガンガン系」の特異なリアリティラインに反発を感じる読者は多いだろう。
『ヴァンパイア十字界』は一見するとその「ガンガン系」のごくありふれた一例と映るところがたしかにある。
強大な魔力を暴走させ一国を滅ぼした吸血鬼の女王アーデルハイトに、封印された彼女を探し求める亡国の吸血鬼王ストラウス、さらにかれが千年のあいだ戦いつづけるかつての愛娘ブリジット、そして、全人類のなかでたったひとりストラウスに対抗する力を持つ女性「黒き白鳥(ブラック・スワン)」と、いかにも「中二病」的といいたくなるような設定がそろっていて、あたかもただ「ハッタリ」や「雰囲気」で物語を演出しているかのように見える。
あまりにも広げた風呂敷が大きすぎて、とても満足に回収し切れるとは思えないような一面があるのだ。
どうせ、ただそれらしい設定をそろえて登場人物を戦わせることに終始するばかりのありきたりな「バトルもの」に過ぎないだろう。冒頭のあたりを読んで、そう判断する人物がいたとしても、わたしはまったく責められない。
むしろ、そういうふうに読むのが当然というものだ。第一話の時点でクライマックスの展開を予想できる人がいるとすれば、それは想像力というより妄想力がたくまし過ぎるというものである。
まさか、ストラウスの目的に、あのようなすさまじい真実がひそんでいようとは――。しかし、この記事ではあくまでネタバレは避けることにした。物語の先の展開についてふれることはやめておこう。
とにかく、この作品、始まりのあたりではのちに待ち受ける雄大無比な展開をまったく想像できない構造になっており、しかもその構造こそが物語をでたらめに面白くしているその本質なのである。もし、そのすべてをここで書いてしまったなら、この作品の魅力は半減することだろう。
したがって、第一巻より第二巻、第二巻より第三巻と、物語はさまざまな謎を秘めつつ尻上がりに面白くなってゆく。いったい、ほんとうにこのすべての謎が解き明かされる結末が待っているものなのかどうか、そう疑ってしまうほどに。
ところが、物語が終盤に至ると、なんとすべての謎は疑問の余地なく解き明かされてしまうのだ。しかも、そこに展開する光景はまさに想像を絶するものだ。
世界を救うため立ち上がったダムピール(半吸血鬼)たちの軍団を敵にまわし、さらには転生を続ける代々の「黒き白鳥」を殺害しつづけ、ただひたすらに愛する妻の封印を解こうとするローズレッド・ストラウスの真意はどこにあるのか?
その「隠された真実」があきらかになったとき、物語はまったく違う様相を見せる。そう、物語を読み進めれば読み進めるほどにつのるある感覚、何かがおかしい、いったい何が――そういうかすかな違和感が積み上がっていったその先に、孤独な吸血鬼王ストラウスが見た地獄がある。
傷つき、血まみれとなったヴァンパイアの王が、その美しい頬に哀しい微笑を浮かべて「それが政策だ」と呟くとき、あまりに凄惨で絶望的な真実の果てに見えるもの――それは、ひとりの傑出した「王」の壮絶なる覚悟である。
そうだ、これはあるひとりの真の王の物語なのだ。王とは何者なのか、どれほどの負担を強いられるものなのか、この物語は容赦なくそのことを描き出す。
かつて、一千年の昔、ストラウスが見たもの、そしてその後の長きときにわたってかれが背負ったもの、本来であれば個人が背負うべきではなく、背負えるはずもないもの、その重さに比べれば、『DEATH NOTE』で神を気取った夜神月なども、しょせんは覚悟が足りぬとすら思われてくる。
そのくらい、ストラウスの人生は過酷であり、その王としての使命は重すぎるのだ。しかし、ここで少しでもそのことについて明かすわけにはいかない。どうか、わたしの言葉を信じて、この作品を読んでほしい。必ず最後にはこの上なく純粋な感動にたどり着けるはずだ。
一篇の優れた「本格ミステリ」として読むべし。
たしかに一見するといかにもリアリティラインが低く設定されているように見えるし、中盤であきらかになる「ある設定」はさらに作品世界のリアリティを崩しているように見えるかもしれない。じっさい、ネットにはそのように評価している人も見つかる。
だが、『ヴァンパイア十字界』の本領は、あきらかにそういったところにあるのではない。それらはあくまでひとつの「背景設定」であり、「ゲームのルール」を成立させるためのコマなのだ。
城平京は本格ミステリ大賞を受賞している優れたミステリ作家である。そして、この作品を最後まで読めば、これがSFでもファンタジーでもなく、本格ミステリの方法論で書かれていることはあきらかだろう。
そして、まさに『ヴァンパイア十字界』はミステリがミステリとしてたどり着くことができる最高の境地へ至っている。わたしはそう考える。
すべての物語は「一千年前、ヴァンパイアの女王アーデルハイトを巡って何が起こったのか」、そのたったひとつの謎から派生している。ただ、見る人、語る人によってその謎には異なるものが見えるだけなのである。
すべての真相を知っているのは赤バラと呼ばれる王ローズレッド・ストラウスただひとり。かれの真意を知る者は敵にも味方にもだれひとりいない。その、暗澹(あんたん)たる孤独の深さよ。
この構造は、映画脚本の世界では、黒澤明の名作『羅生門』から採って「羅生門効果(ラショーモン・エフェクト)」と呼称される種類のものだ。
事実は一つ。しかし、真実は人の数だけある。だからこそ、あらたな語り手があらわれるたび、それは異なる姿を見せる。
だが、そうなのであれば、そのたびごとに異なったかたちを見せるいくつもの「真実」のそのさらに向こうにある唯一の「事実」とは何なのか。そのすべてが解き明かされるとき、ついに最後の悲劇の幕が開く。
いったいだれが悪かったのだろう、何をまちがえていたというのだろう、なぜこのようなことになってしまったのだろう、読後、考えさせられることは数多い。
しかし、一つたしかにいえるのは、それらすべてを乗り越えたストラウスの覚悟の崇高さだ。
かれこそは至高の王、君主のなかの君主。ヴァンパイアたちの夜の王国を統べるために生まれ、その覚悟を背負って育ったただひとりの人物。結果として国を滅ぼすことになってしまってもなお、それは揺るがない。
そのことは、物語を読み終わったときにはだれもが実感しているだろう。
たしかに『スパイラル』も『絶園のテンペスト』も『虚構推理』も傑作だし、きわめて素晴らしい作品といえるのだが、それでもぼくが『ヴァンパイア十字界』こそ城平京の最高傑作だと信じるのは、そのどこまでも哀しく凛然とした英姿がいつまでも記憶に残るからだ。
物語の中盤において、ストラウスは想い人の復讐のためにかれのいのちを狙い、五十年にもわたって地獄を見てきたと語る若者に対し、冷たい目で語る。
「大事なものを失ったのがどうした 這い回ったのがどうした 復讐を否定されたのがどうした それくらい私だって見たぞ ――いや それ以上のものさえ私は見ている」と。
その言葉はまさにほんとうなのである。一千年前の「その事件」において赤バラの王が見たもの、それからずっと見つづけているものは、ただ愛する者を失うといったあたりまえの悲劇の次元に留まるものではない。
だが、まさにそうであるからこそ、かれはしんじつ気高い王なのだ。はたしてひとりの人間がこれほどの重荷を背負うことは正しいことなのだろうか。読後には、何ともいえない重いものが残る。
決して気楽に読み捨てられる作品ではない。だが、だからこそこれは本物の傑作だ。読書人生のすべてをかけておすすめする。『ヴァンパイア十字界』、これこそはまさに読むべき物語であり、広めるべき作品だと。
どうかお願いだ、あなたも読んで、この「なぜか埋もれてしまった大名作」を世の中に広める伝導の使徒のひとりになってほしい。何もかも終わったそのあと、赤バラ王の伝説の全貌を知り、それを語り伝えることができるのは、ただ、読者たるわたしたちだけなのだから。
\ よかったらこの記事をシェアしよう! /