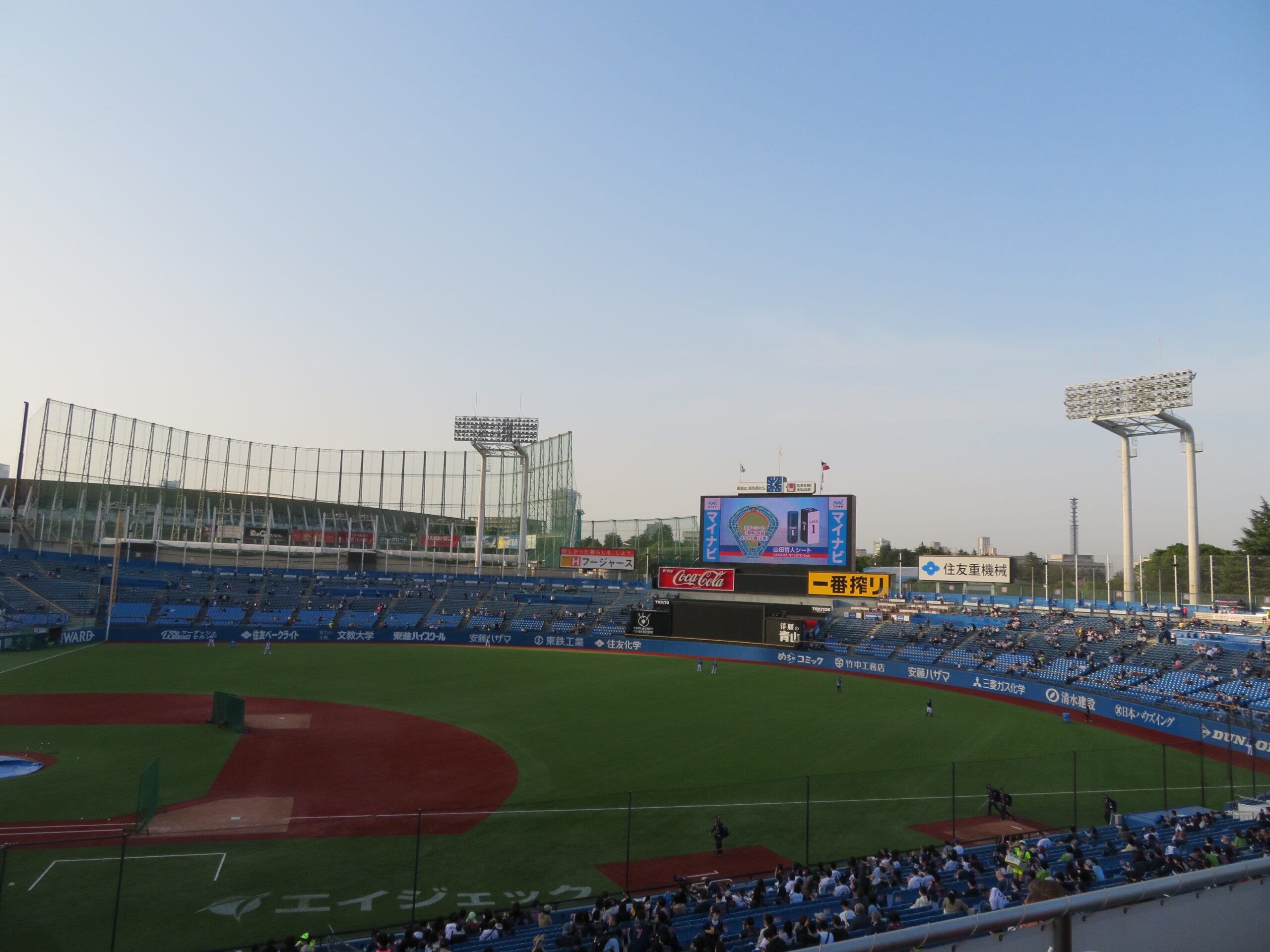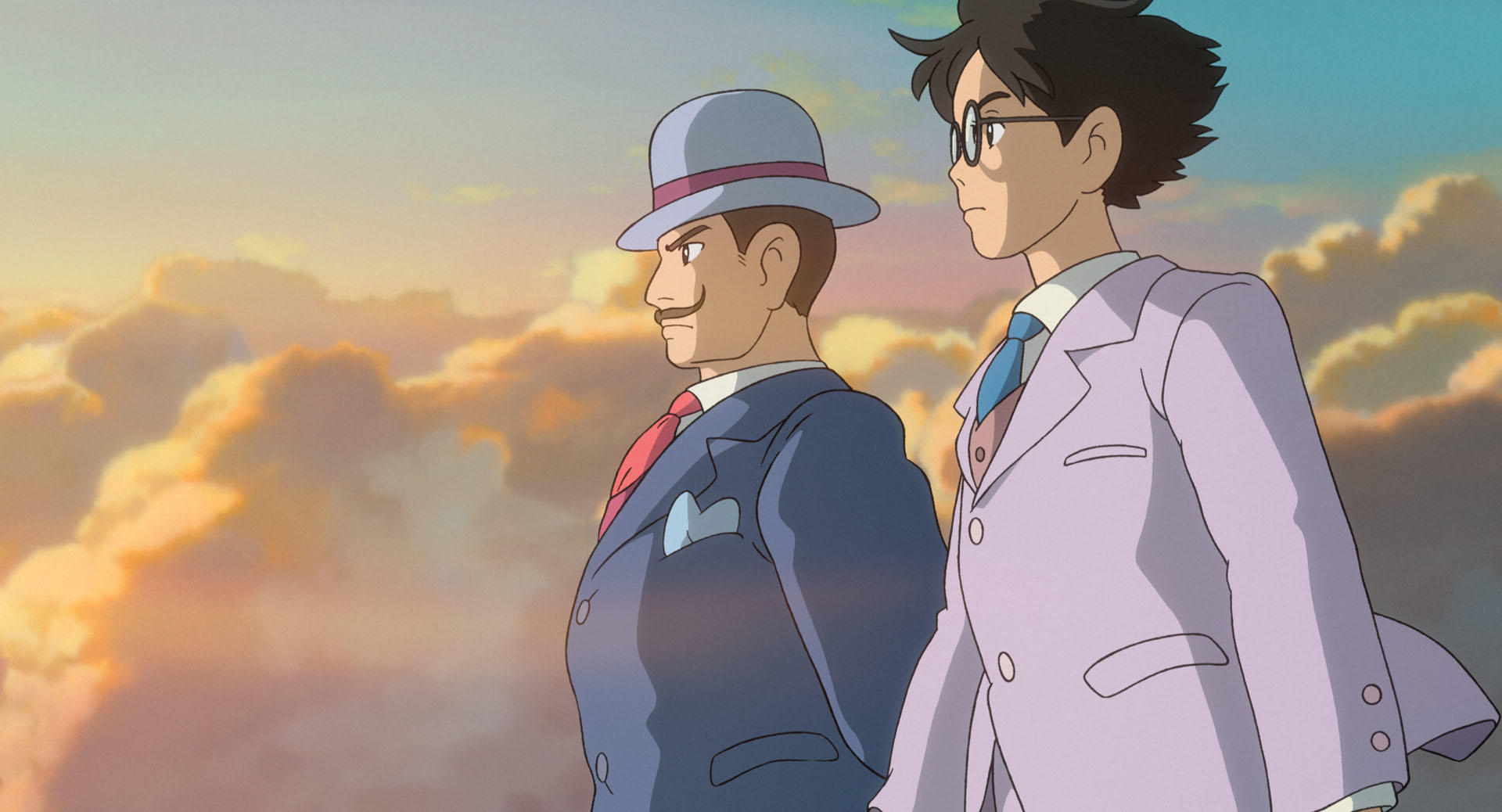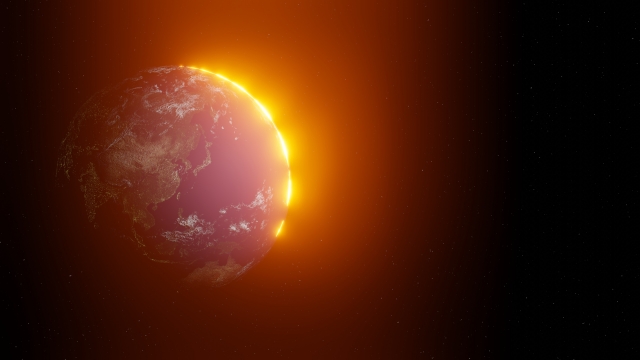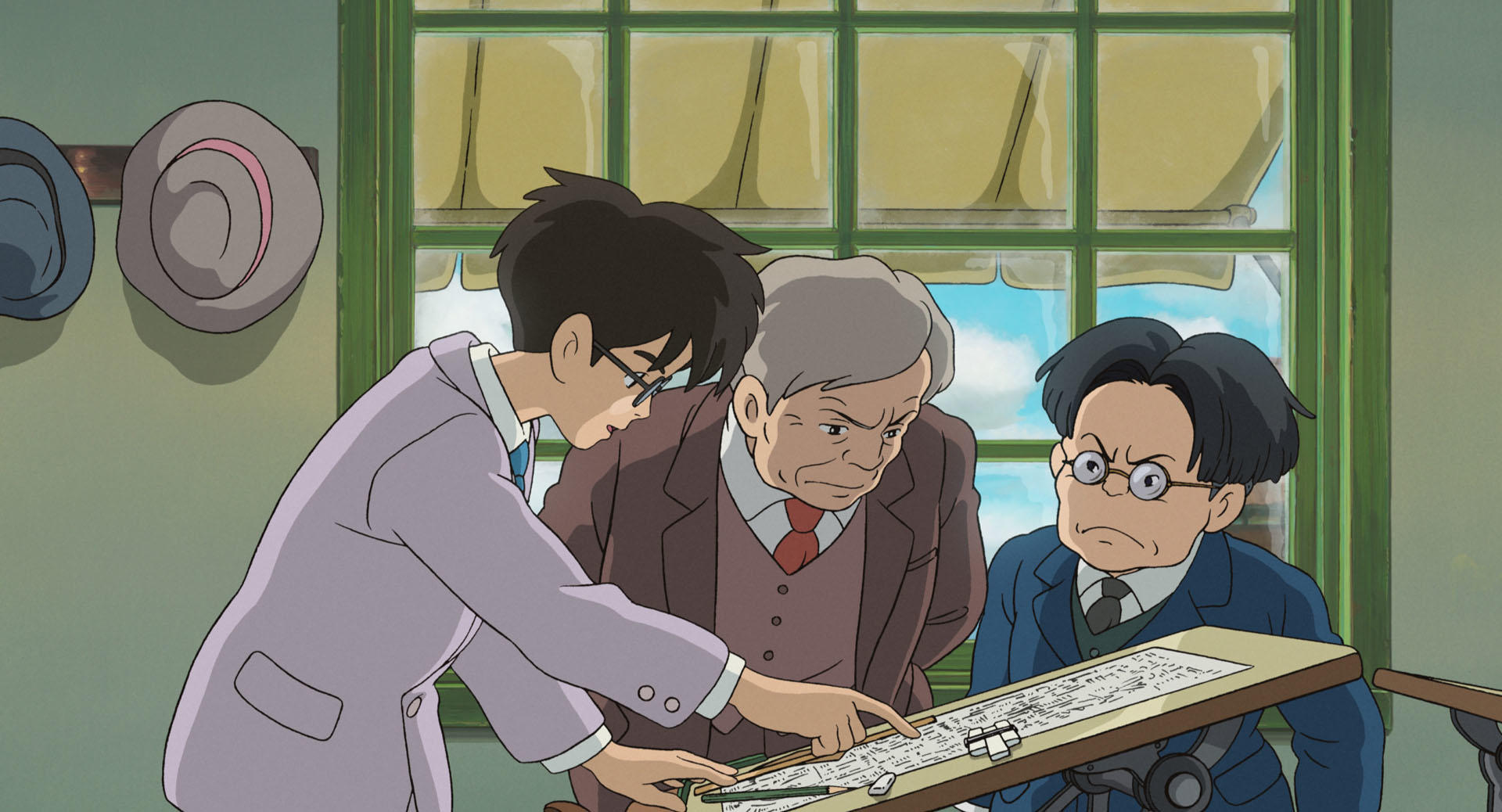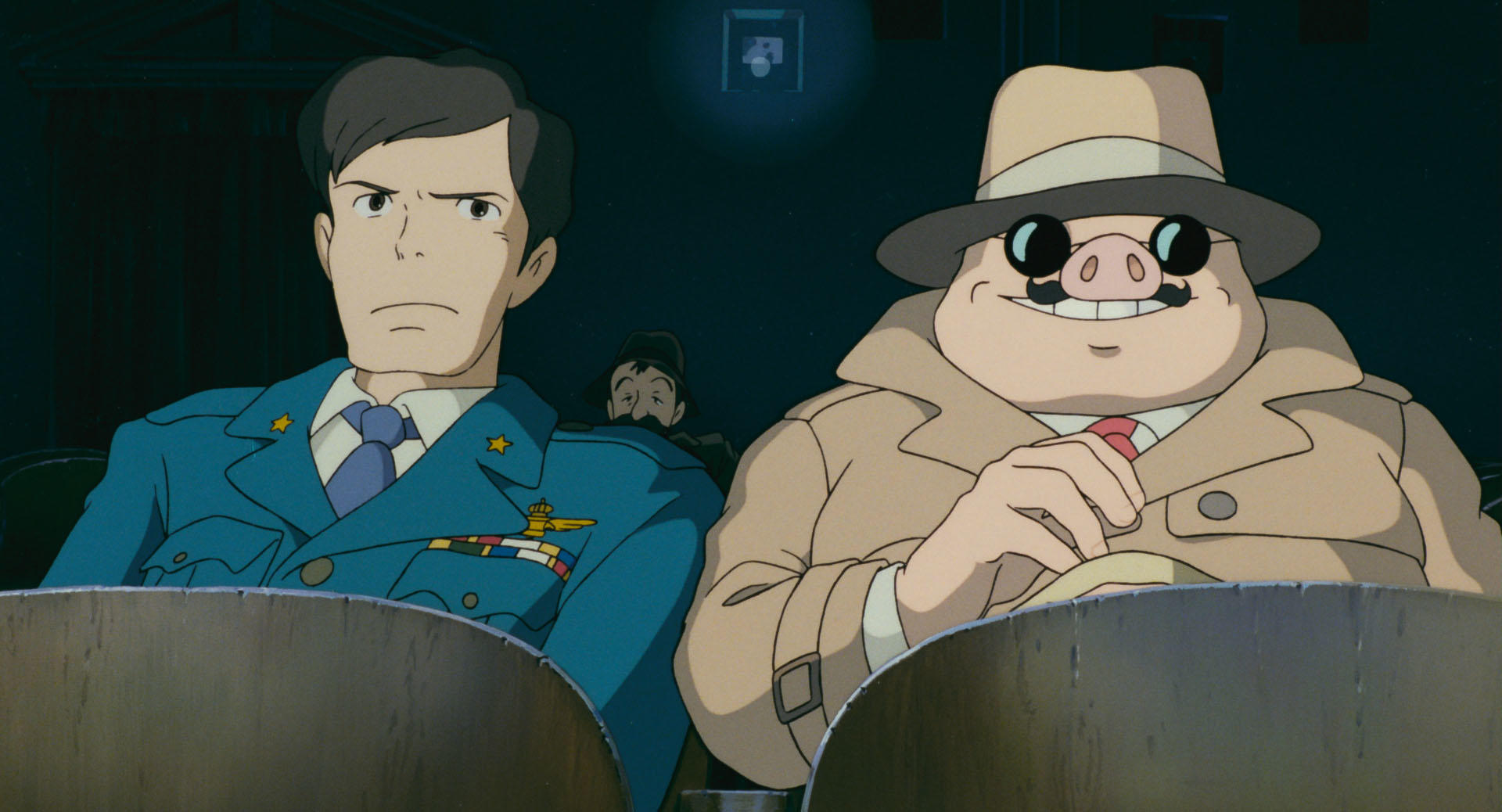アリストテレス以来二千年! いまだに完成しない作劇論のセカイを語る。

突然だが、なにか物語を生み出してみたいと思ったことはないだろうか? それも、波乱万丈、読む者を大いに笑わせ、泣かせ、感動させ、ページをめくる手を止められないという思いにさせる最高の一品を。
ぼくはある。何度もあるのだが――ざんねんながら天なる神はぼくを地上に落とすとき、創作の才能を込め忘れたらしい。間抜けなやつ。その神さまのしょうもないミステイクのせいで、ぼくにはまるで物語を紡ぐ能力がない。
幾たびか書いてはみたのだが、どう考えても傑作には程遠く、もっともよくいって駄作と凡作の中間くらいといったところ。自分で読んでみてすらまったく面白くないので、自分以外の人はもっと面白くないに違いないと思える、そういうクオリティだ。
異世界転生でもして何かチートを授かったりしないかぎりこの現状は変えがたい。それでも、どうにかする術はないかと思っていろいろと調べてみて行き着いたのが、「作劇論」の世界。
いわゆる「ハリウッド脚本術」あたりから「ミステリの書きかた」、「ティーンズラブ小説の書きかた」といったものまで、片っぱしから読みあさった。
その結果、ぼくの筆力がどれほど向上したかというと、まあゼロではないかな、くらいなのだが、「物語の構成のしかた」について学ぶことそのものは面白かった。
じっさい、ある程度の才能がある人が読めばそれなりに役立つのかもしれない。たとえばベストセラー作家の乙一はハリウッド脚本術の「三幕構成」の技法をもとに小説を書いているという。
いったいあの魔法のように神秘な作品たちがハリウッド脚本術ごときでほんとうに書けるようになるものなのかどうか大いに疑問だが、まあ、「何とかと作劇論は使いよう」、天下の乙一がもちいればありきたりの脚本術も不思議な切れ味を示すものなのかもしれない。
気分だけは天才ストーリーテラーの凡人としてはただただ感心するよりほかない。いや、すべてが生まれ持った才能で決まるというわけでもないのだろうが……。
そういうわけで、今回はアリストテレス以来の「作劇論」について少し話をします。よろしく。
物語理論の歴史二千年は『詩学』に始まる
さて、現代につらなる作劇論は、その博学アリストテレスの『詩学』を発端とする。現代の創作理論はそのほとんどがこの本の影響を隠然と受けていることになる。いやまあ、おそらくこれより古いテキストもあるのかもしれないが、ぼくは知らない。
とりあえず、この本が現存する物語の批評理論としては最古に近いもので、現代のストーリーテリング理論の基本となっていることはたしかなようだ。
「始まって」、「色々あって」、「終わる」、いわゆる三幕構成もこの『詩学』から来ているのだとか。
また、もし、あなたに少しでも文学や演劇についての知識があるようなら、ミメーシス(模倣)やカタルシス(浄化)といった言葉を耳にしたことがあるのではないだろうか。こういった概念も『詩学』伝来のものだという。
つまり『詩学』は、古代ギリシャのやたら偉大な悲劇についていまに語り伝え、現代の物語にすら甚大な影響をあたえている作品(集)なのだ。
ちなみに欠けている部分もあって、喜劇に関するところは失われたといわれている。だが、まあ、悲劇に関しての部分だけでも後世に大きな影を落としているわけである。
面白いのは、それから二千年以上もの時が経ち、古代ギリシャの栄光もことごとく失われ、いまや科学の時代が来たというのに、作劇論が完成するけはいはまったくないということだ。
いまなお、ある個人の天才を凌駕するほど完成度の高いストーリーテリングの方法論は存在しないと思う。
たしかに、ハリウッドやらロンドンやらではきわめて洗練された物語づくりのための理論を教育しているという話は聞く。それはほとんどサイエンスの域に達しており人間心理を的確に分析して「より面白い物語」を生むための具体的な方法論を導いているらしい。
が――そうはいっても、いまなお、その黄金の法則にのっとっているはずのハリウッドのシナリオですら、「よくこんなひどい話を考えられましたね?」といったレベルのものがまざってしまうことがじっさいにある。
その罪はその作品にかかわったビジネスマンやエコノミストにあり、シナリオライターにはないのかもしれないが、それにしても、この輝かしい21世紀に至ってなお、「面白い作品」を生み出すための方程式が明確にさだまっていないことは奇妙とも思える。
一作が何千億円というマネーを揺り動かすにもかかわらず、映画は結局、職人かたぎの監督や脚本家の個人的な資質に依存することをやめられていないのだ。
これは、すごいことではないだろうか。ぼくにはちょっと信じられないような話である。何が面白いのか、少なくとも商業的にヒットするのか、明確に見抜く魔法の目はいまだこの世に存在しないのだ。
何しろ、出版市場に冠たる大ベストセラーとなった『ハリー・ポッター』ですら、当初もちこまれた出版社では見向きもされなかったのだから。
「こういう作品がウケそう」という基準がまったくないわけではないだろうが、どうもあてにならないことはなはだしいといわなければならないようだ。
じっさい、記録的な商業的失敗作となった『ジョーカー』の続編のようなこともいまだに絶えない。
もし、ほんとうにハリウッド脚本術が科学の域にまで洗練されているなら、そのようなことは決して起こらないだろう。結局のところ、作劇論やら脚本術やらは、いまだに科学よりは錬金術のほうにより近いのではないだろうか。
世の作家や脚本家たちがいいかげんなことをしているといいたいわけではない。ただ、人知を尽くしたあとは天命を持つしかない仕事というものはあるもので、物語づくりもそれに近い領域のビジネスなのではないかと思えるのである。
「ヒーローズ・ジャーニー」理論さえも古びたものに
とはいえ、大海原に乗り出すときはだれでも羅針盤がほしいものだ。たとえ、完全に正確な方角を指し示してくれるわけではないとわかっていたとしても。
そのために古色蒼然たる物語からひっぱり出してきたのが、たとえば、いわゆる「神話の法則」である。
これは「英雄の旅(ヒーローズ・ジャーニー)」などともいわれるもので、すべての神話に共通する(と主張されている)ある「法則」にのっとって物語を書けば、あら不思議、この何千年ものあいだほとんど進化していない人間の脳髄の「面白さ」を感じ取るポイントを絶妙に刺激し、過度に興奮させるという話。
脚本術の業界では、かの『スター・ウォーズ』はこの神話理論にのっとって物語を編み出し、みごと大ヒットになったと伝えられている。
作劇理論にはどこか錬金術めいて怪しげなところがあることはたしかかもしれないが、まったくのオカルトというわけではないことがここからもわかる。
しかし、千年一日のごとく変わるはずもない人間心理を捉えた神話由来の「法則」といえど、やはり完璧ではありえない。
この「法則」にしたがって物語を書くとたしかに壮大な神話的キャラクターやらストーリーを生み出すことはできるようなのだが、いっぽうで繊細な人間的生々しさを欠くことになってしまうようでもあるのだ。
『スター・ウォーズ』はまさに「現代の神話」ともいうべき魅力的な一作ではあるが、同時に、そうであるがゆえの心理的なディティールの甘さをも備えている。
そして、シリーズが「前日譚三部作」、「後日譚三部作」と続くにつれ、その神話的なスケールの大きさが失われて行っていることはだれの目にもあきらかなところだろう。
これは結局、現代の観客の目に神話的スケールの物語が物足りなく感じられるからこそそうなっていっているわけで、必ずしもジョージ・ルーカスなどが無能だということを意味しない。
アリストテレスもシェイクスピアも、完璧な作品を生み出す具体的な方法論を書き残してくれたわけではないから、こういう事態が往々にして起こるわけである。
もちろん、映画にお金を出す側としては確実にその資金を回収できなければ困るわけで、そのために膨大な金額をつぎ込んで優秀なシナリオライターを養成しているのだろう。
その結果、たしかにハリウッドの脚本はだいぶソフィスティケーションされていて、最近、そこまでひどい映画を観る機会は少なくなっているように思える(恐ろしいことに、先述したように、まったくのゼロにはならないわけだが)。
とはいえ、くりかえすが、そのハリウッドですら確実に素晴らしく感動的な物語を生み出せるというわけではない。また、鵜の目鷹の目でものすごいアイディアをさがしてはいるだろうが、どうにも凡庸な作品をなくしてしまうことには成功していないようでもある。
それがエンターテインメントなのだ、といえばそれまでだ。しかし、なぜこのようなことになっているのだろう?
「幼年期の終り」は来るか?
ひとつには、もちろん、常に時代は変わりつづけていて、人の心もそれに合わせて変化していっているからだろう。
ストーリーテリングの方法論にはもちろん普遍的なところもあるが、それがすべてとはとてもいえそうにない。ある社会において爆発的にヒットする作品を生み出すためには、どうしてもその社会にアジャストした方法論が必要とされる。
ただ「普遍的」なだけでは十分でなく、それに加えて「同時代的」である必要もあるのだ。
仮に、批評家ならだれもが認めるような名作を生み出すことに成功したとしても、それが時代を捉えていなければ、商業的には鳴かず飛ばずに終わるということもありえないわけではない。
わずかな発表時期の違いによってビジネスチャンスを失ってしまった傑作はいくらでもあることだろう。その反対に、まさにその「時代の潮目」を読み切って、あるいは偶然にその流れに乗って大ヒットした作品もあるはずだ。
そのことは、たとえば数年前の『鬼滅の刃』のブームを思えばだれにでもわかるのではないだろうか。
『鬼滅の刃』は、もちろんきわめて優れた作品ではある。しかし、ちょっと時代が違っていたら、あそこまでのウルトラスーパーヒットにはならなかったはずだ。
結局、ヒット作には「時代と寝る」一面がどこかに必要なのであって、ただ普遍的な王道の面白さというだけでは十分とはいえないのである。
そして、もうひとつは、小説であれ映画であれ、あるいはマンガやアニメ、演劇などであれ、新しく世に出るストーリーには何らかの「未見性」が求められるからだろう。
つまり、どんなに優れたストーリーであっても、すでに世の中で先行する作品が知られていれば、それは「二番煎じ」としか認識されない。そのため、あとに発表された作品ほど、オリジナリティを発揮するために苦労することになる。
ウィリアム・シェイクスピアはたしかに破格の天才物語作家だった。しかし、かの大劇作家が現代に生きていたとしたら、やはりまったく新しい物語を生み出すためには苦労するのではないだろうか?
シェイクスピアの時代から数百年、そのあいだに膨大な物語が生み出され、「まったくあたらしい物語のアイディア」の可能性はより少なくなっているのだ。
つまりは、ストーリーを語るとはどうしようもなく「差異化」のゲームなのだということ。「面白い」だけでは十分ではなく、「いままで見たことがある他の作品とは違う面白さで面白い」必要があるわけである。
これでは、どんなに確実な創作の方法論を確立したとしても、あっというまに古びてしまうことが道理だろう。
じっさい、「神話の法則」はいまでは非常に古く感じるし、そのあとに生み出された、たとえば「セーブ・ザ・キャットの法則」あたりもいまではちょっと古くさい。
ようするに、物語づくりの方法論は、たまたま錬金術にとどまっているわけではなく、わけあって科学に昇格できずにいるということなのだ。
もちろん、創作は魔法ではない。ちゃんとそこには理論もあれば、手順も(ある程度のところまでは)さだまっている。しかし、しょせんそれが科学になる日は永遠に来ないのかもしれない。
ある方法論が明快に確立されたら、観客はその方法論を前提に作品を見るわけで、作劇論の洗練とは、そうとうにたちの悪いいたちごっこというより他ならない。
少なくともいまのところは、作家や批評家の怪しげな「カン」以上にあてになるやりかたは存在しないように思える。
だが、逆にいえば、だからこそ創作は、芸術は面白いともいえる。いつの日かAIがこの人間の限界を打ち破り、無限に新鮮な物語を生み出す日が来るかもしれないが――とりあえず、それはいまではない。
いつかは物語を作り、あるいは物語について語るそのやりかたがアリストテレスの影響から完全に抜け出す日は来るのだろうか?
その真実はわからないが、とりあえずぼくはその日がなるべく遠くであるといいなと思っている。
あしたよりあさって、あさってよりしあさって、AIよ、どうかぼくたちからおもちゃを取り上げないでくれ。ぼくたち人類はまだ幼年期にあって、もうしばらくのあいだは物語で遊んでいたいのだから。
\ よかったらこの記事をシェアしよう! /