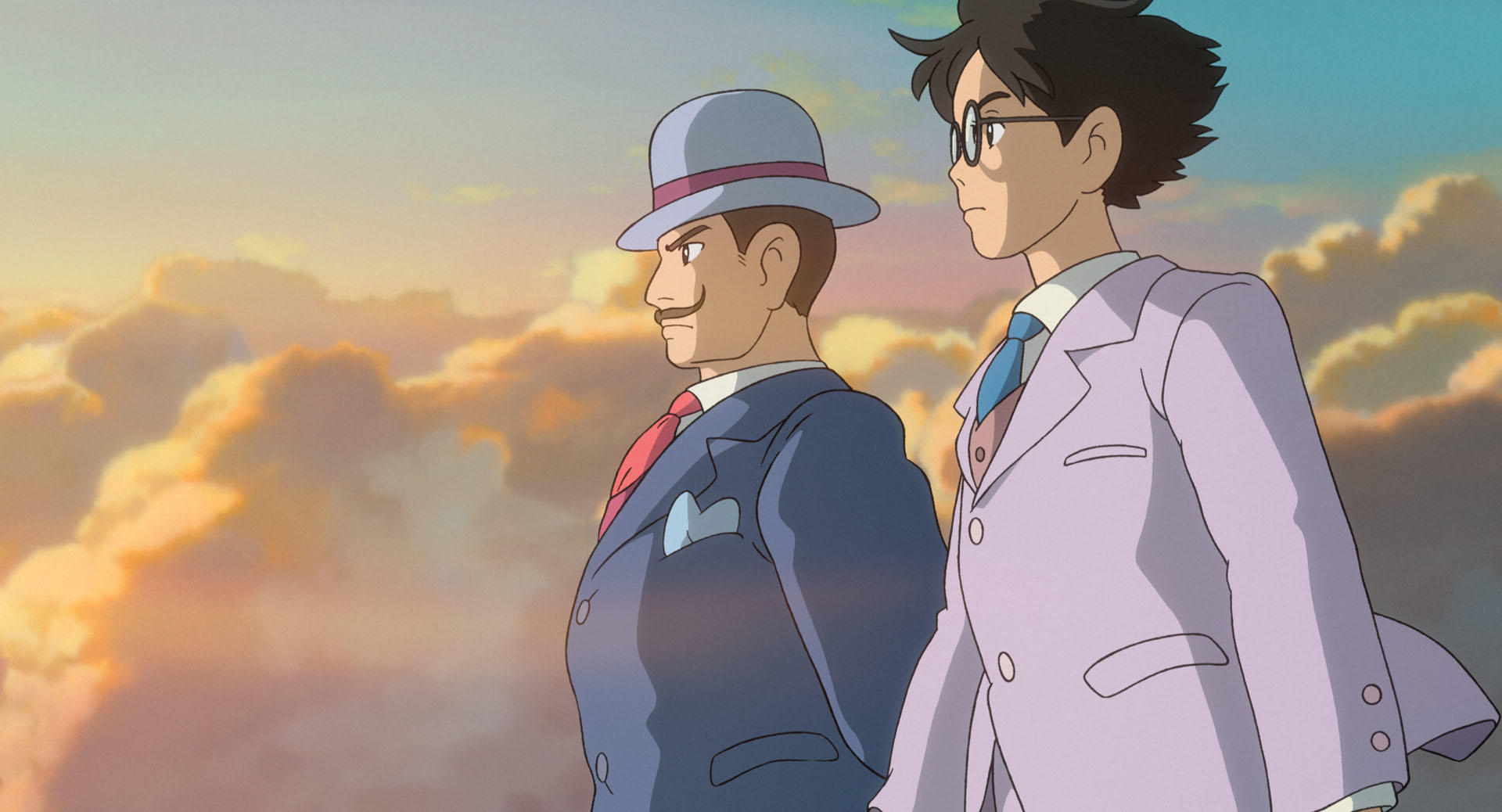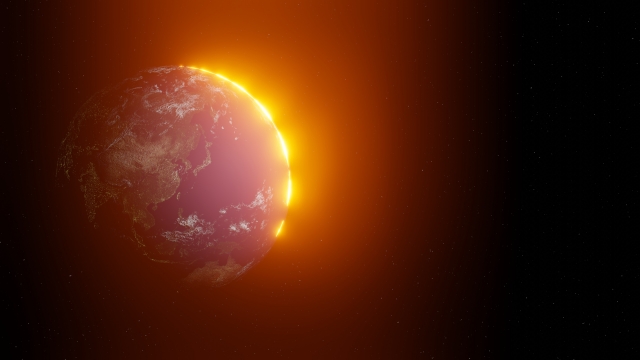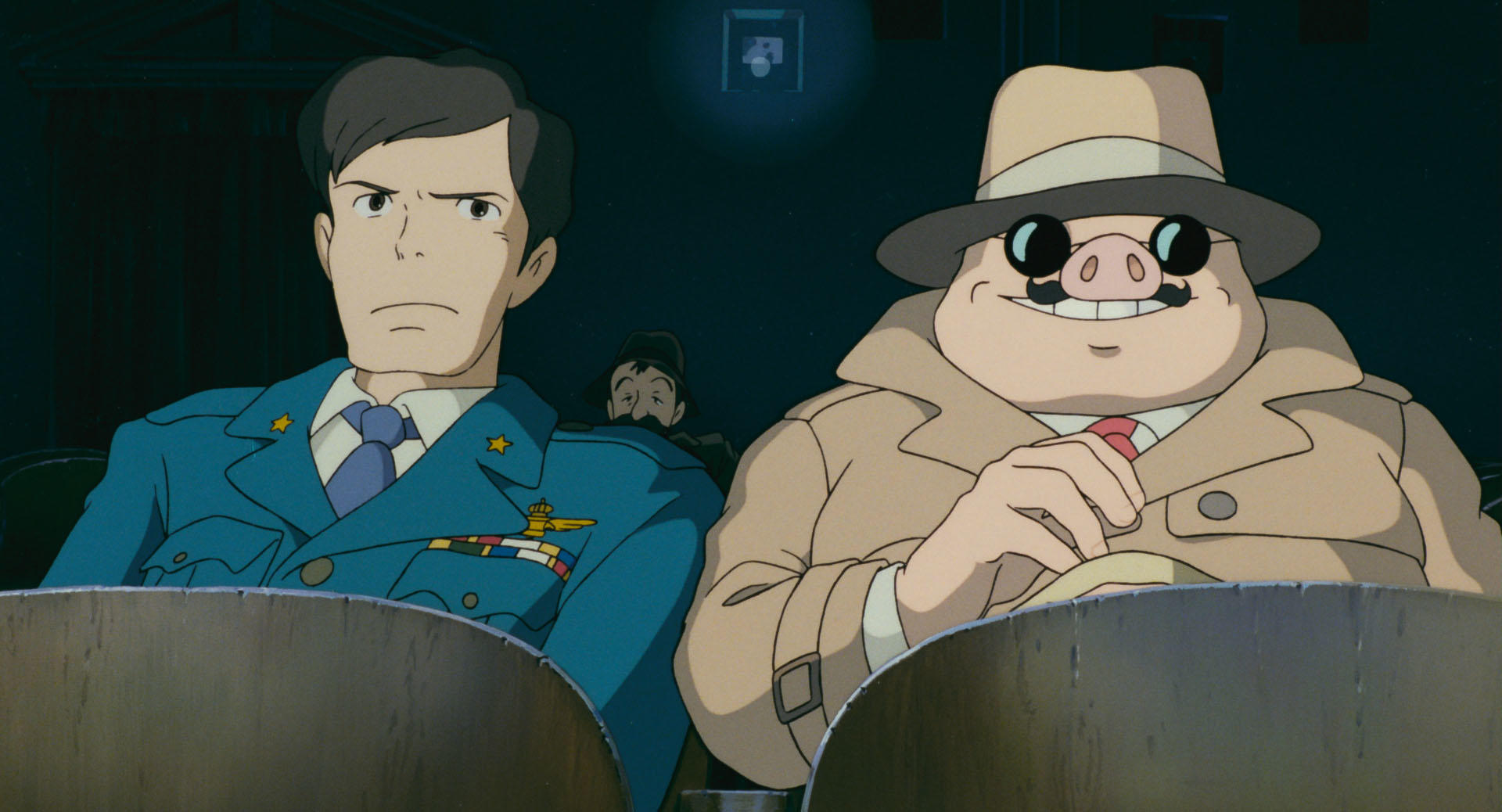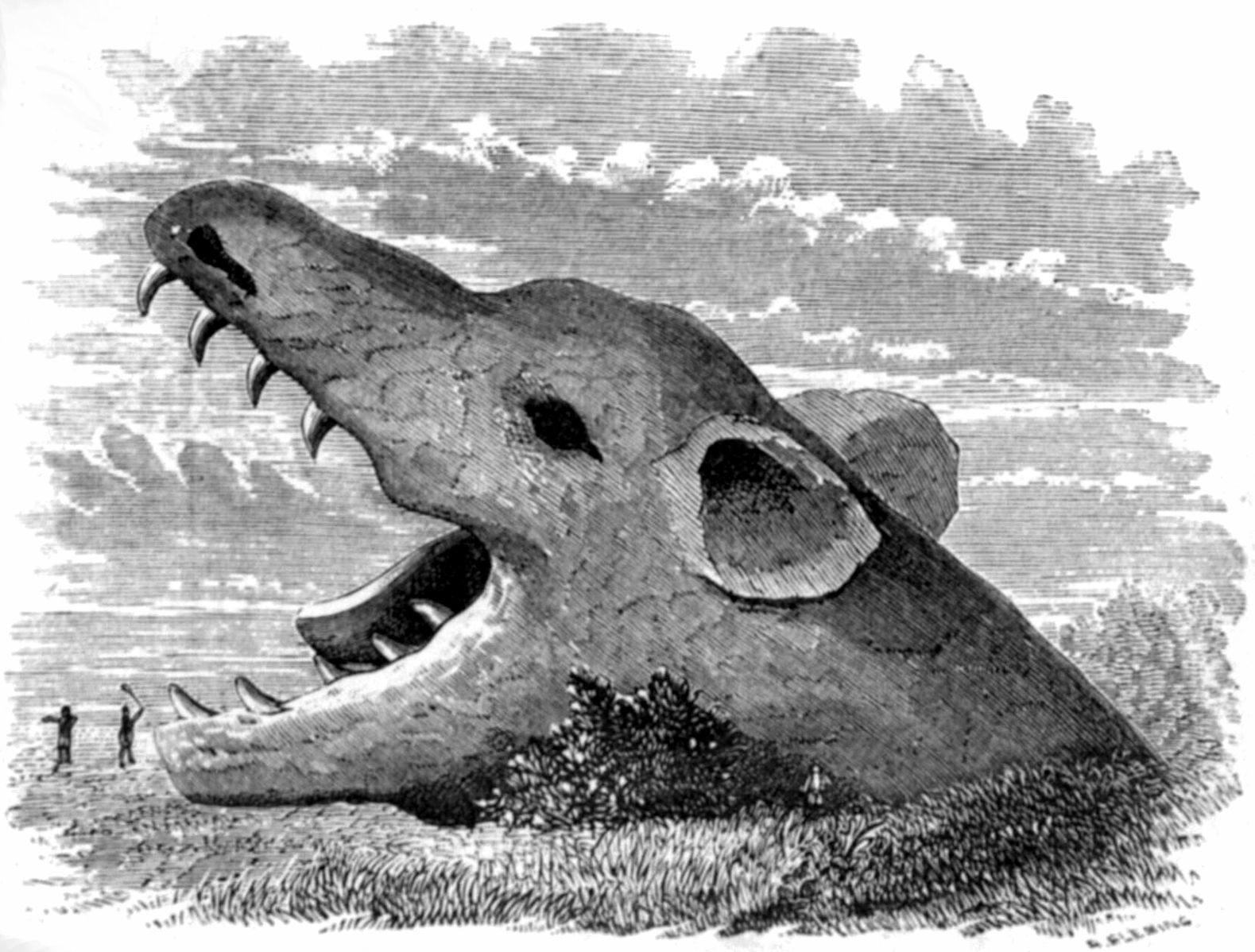
映画に出てくる犬は生きていても死んでいても天使のようだ。

犬はいいですね。
特にみちばたで出会う犬はいい。不意にあらわれる犬は天からの恵みのようであり、つらくかなしい毎日を過ごすわれわれにとっての清涼剤です。
そういうわけで、映画を観ていても犬が出てくるとうれしくなります。ポスターや予告編を見て、犬が主役とひとめでわかるような映画に出てくる犬ではありません。それはそれでそういうもののよさはありますが、脇役だったり、なんなら通りすがりのようにワンカットしか出てこないほうがよろこばしい。
わたしが映画に出てくる脇役的な犬を気にしだしたのは、おとなになり、子どものころあれほど豊かだった感受性が摩滅し、それまでこわくて観られなかったホラー映画を観始めたころだったでしょうか。
恐怖描写に耐性があったとしても、動物が死ぬシーンに耐えられないヒトであれば、ホラー映画はまず避けるべきです。ホラー映画ではとにかく動物がよく死にます。なかでも、犬は死にまくります。

たとえば、スラッシャー映画の古典『ハロウィン』。このシリーズでは殺人鬼であるマイケル・マイヤーズによって五作目までのほぼ毎回犬が殺されていくことで有名です。三作目では殺されませんが、それはマイケルが出演していないせい。
第一作の『ハロウィン』(ジョン・カーペンター監督、1978年)を見てみましょう。
殺人鬼マイケルがある住宅の庭に立ってベビーシッターの女性を不気味に監視していると、不審者を嗅ぎつけたその家のジャーマン・シェパードに吠えかかられます。マイケルは無慈悲にも番犬に手を下しますが、ベビーシッターは異変に気づきません。そうして、彼女もまたマイケルの犠牲者となっていくのです。
『ハロウィン』のこのくだりには、ホラー映画における犬殺害描写の典型的な要素が詰め込まれています。
殺人鬼や怪物の魔手が平和な住宅街に迫りつつある。それをいち早く感知した犬が侵入者に吠えかかり、あえなく殺されてしまう。そして、それが直後に人間たちを襲う惨劇の先触れとなる――。
ホラーとそのサブジャンルで殺される犬たちは、おおむねこうしたバリエーションにおさまります。『JAWS』(1975年)、『ファニー・ゲーム』(1997年)、『死霊館』(2013年)、リメイク版『死霊のはらわた』(2013年)、『M3GAN ミーガン』(2022年)……。そうそう、『13日の金曜日 PART2』などは、そうしたクリシェを逆手に取りつつファンのあいだでも意見のわかれるオチにしていますね。
ヒトのパートナーでありつつも「文明」と「自然」のはざまに位置する犬は、ヒトに先んじて超自然的ななにかを嗅ぎつけ、そして身を挺してその先の展開をヒト(と観客)に示すのです。犬がヒトに社会的にも心理的にも近しい存在だからこそ、観客は犬が殺されるシーンに怖気をおぼえます。
さように、ヒトと犬の運命はつながっているのですね。ロブ・ゾンビ監督のリメイク版『ハロウィン』(2007年)では殺される犬を出さなかったわけですけれど、ベビーシッターの顛末もオリジナル版から変更されている事実は興味深いところでしょう。

ところであなたはいま、こうお考えかもしれません。
「犬はいい」という話のはずなのに犬が死ぬ映画の話をするのは……よくないのでは?
とんでもない。犬が死ぬ劇映画ほど、犬がいてよかった、とおもえる映画はありません。なにせ、スクリーンのなかで死んでいる犬は実際には死んでいないのです。
ハリウッド作品ともなると、専門機関の監視のもと、撮影現場での動物の扱いは厳格に管理されています。映画の犬はどんなに無惨な最期を遂げようと、カットの声がかかるとひょっこり立ち上がり、尻尾を振ってトレーナーや俳優に頭をなでてもらっているのです。
メイキング映像などで見られるこんな瞬間以上に、犬が生きていてよかった、生きている犬はよい、と感じられる瞬間がほかにあるでしょうか? 『ハロウィン』の監督であり、『遊星からの物体X』(1982年)で犬好きたちに生涯もののトラウマを植えつけたジョン・カーペンターも、現場では俳優犬をリスペクトし丁重に扱っていたことで知られています。
疑り深いあなたなら、「いや、実際に動物たちが現場でどう扱われているかは観客にはわかったもんじゃない」というかもしれませんね。「アレハンドロ・ホドロフスキー監督の『エル・トポ』(1970年)では、実際に大量のウサギが虐殺されていたというではないか」、と。
そんな不安な魂に有用なのがインターネットです。印象的な俳優犬を映画で見かけたならば、即グーグルに「映画名 犬」で検索しましょう。すると、その犬の元気な姿がたくさん出てきます。
最近の映画であれば、アカデミー賞にもノミネートされたジュスティーヌ・トリエ監督の『落下の解剖学』(2023年)。この映画には、犬がもがき苦しむ場面が出てきます。見ていて誰しも心かき乱されるシーンです。演技とはいえ、ここまで苦しませて大丈夫なのか……? と疑いのひとつもわくでしょう。
そこで「messi(俳優犬の名前) anatomy of a fall(『落下の解剖学』の英題)」で検索をかけます。するとどうでしょう、あの犬が映画賞の授賞式で行儀よくおすわりしたり、撮影現場でキョトンと佇んでいる姿がなんぼでも出てきます。なんなら、映画で見せた演技を再現するインタビュー動画だってあります(https://www.youtube.com/watch?v=EHH8kgRrgQ0)。

まあ、それでもなお「たとえフィクションのなかであっても犬が苦しむのは見たくない!」という方はいらっしゃるかもしれません。実際、アメリカ映画ではホラー以外のジャンルだと「映画のなかで子どもは殺せても、犬は殺せない」とジョークのネタにされるほど犬は不可侵な聖域です。
冒頭で「犬の死を見たくなければホラーは避けろ」といいましたが、逆にいえば、ホラーさえ見なければそうそう映画で犬の死を目にはしません。それでもなお心配な向きには、「その映画の劇中で犬が死ぬかどうか」が調べられるDoes The Dog Die?というサイトもあります(全面的に信頼できると言い切れないサイトではありますが)。
このように、意外にヒトは映画の犬を気にします。それだけ、犬は映画というメディアにおいて重要なポジションを担っているわけです。それらはあらゆる場所で生身においても記号においても犬が商品として扱われている証しのひとつですが、ひとまずはそのような物悲しい見方は棚上げしておきましょう。
それで、犬はいつごろから映画に現れたのでしょうか?
答えは、「最初からいた」です。
リュミエール兄弟の「工場の出口」(1895年)という、フランスの工場労働者たちが業務を終えて工場の出口から出てくる様を撮った短篇があります。よく「世界で最初の映画」のひとつとして数えられる映像で、いくつかバージョンがあるのですが、ここに犬も登場します。しかも二頭。

一頭は出口の左側に寝そべり、もう一頭は工場から出てきます。二頭ともいったんは画面から退場するのですが、工場から出てきたほうはカメラの前へと舞い戻り、人間たちの退勤風景を眺めつつ歩き回っていきます。
「工場の出口」はなにげない日常をとらえたドキュメンタリックな映像にみせかけて、実は数々の「演出」がなされていたというのはよく指摘されるところですが、もしかするとこの犬も画面の外にハケたあとで「おい、戻れ」と指図されたのかもしれません。

というのも、動いている犬はそれだけで画になる。たとえば、ジャック・タチの『ぼくの伯父さん』(1958年)では、冒頭の数分間を本筋と関係のない犬たちが街路でうろつく様子に割り当てていますが、これがなぜだかすばらしく感動的です。天使が実在するなら、このようなステップを踏んで歩くに違いない。あなたもきっとそう感じます。
映画のなかで動く犬を観るのは快楽的です。いっぽうで、「工場の出口」での犬がそうであったように、映画のなかの犬は人間を観察する側でもあります。かつて、飼いネコに風呂上がりの裸を見られて羞恥心をおぼえた経験をながながと綴った哲学者もいましたけれども、価値判断を含まない動物の視線はときに他人の眼以上にヒトに負い目をあたえます。
最近の映画でいえば、『関心領域』の犬は語るに値するでしょう。ナチスドイツ絶滅収容所の所長一家の日常を淡々と描いた作品です。所長の妻はユダヤ人たちから没収したオシャレな衣服を横領していて、寝室の鏡の前でたのしげに試着したりする。すると、そこに飼い犬であるワイマラナー(ドイツの貴族が生み出した犬種です)が入りこんできます。きゅうに居心地のわるさをおぼえた彼女は部屋から犬を追い出し、追い出された犬はわけもわからず閉ざされた扉の前でクンクンと鼻を鳴らします。
所長の妻は鏡に映る自分のおぞましさを自覚していなかったのに、自分に懐いているこの犬の存在をプレッシャーに感じてしまったんですね。犬の眼は鏡よりヒトの姿をただしく映すわけです。
この写し鏡としての犬が行き着くところまで行くと、犬はヒトのメタファーとなっていき、ヒトは犬のメタファーとなっていきます。まさしく、『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』(1985年、ラッセ・ハルストレム監督)。
こうした犬とヒトの合一の元祖はなんといってもチャールズ・チャップリンの「犬の生活」(1918年)でしょう。チャップリン演じる哀れな失業者が似た境遇の野良犬を拾い、自分もまた野良犬のような生活を送るお話です。

映画においては、ヒト自身がそうであるように、犬もまた物語を語るための道具のひとつです。ある意味で、そこに本物の犬はいません。擬人化され、記号化され、象徴性が増幅された犬の姿しかスクリーンには映らない。だからこそ、われわれはより濃密なヒトと犬との関係をそこに見出せるわけです。
あなたは映画の犬になにを見出しますか?
それでは、よきドッグ・ライフを。
\ よかったらこの記事をシェアしよう! /